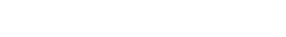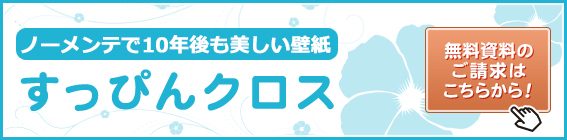クロスの貼り方、注意点を詳しく解説
「クロスのDIYつて、簡単なの?」
「注意点や、必要な道具とか準備は?」
最近のDIYブームで、
気軽に壁紙を変える、壁紙を楽しむ文化に
シフトしつつあります。
初心者でも簡単にDIYで貼れる壁紙もあれば、難しい壁紙もあります。
しかし、一言でクロス・壁紙と言っても様々な種類があるのはご存知でしょうか?
今回はよく使用される壁紙の種類や、DIYで壁紙を貼る際に必要な道具、壁紙の種類別の貼り方を詳しくご説明いたします。
アトピッコハウスには、すっぴんクロスという織物壁紙がありますが、
このクロスは、DIY出来ません。
特徴としては、丈夫で長持ちし、特別な掃除が不要で経年変化が美しいといったことが上げられます。
▶破れにくく丈夫で長持ち、アトピッコハウスの経年変化が美しい織物壁紙「すっぴんクロス」の詳細は、こちら
目次
クロスにはビニールや紙、織物などの種類がある
自然素材の内装材専門メーカー、アトピッコハウスの内藤です。
クロスの貼り方の前にまずはどんなクロスの種類があるのか知ることが大切になります。ではここで一般的な家庭で多く使われる代表的なクロスをご紹介します。
ビニールクロスとは
ビニールクロスとはその名の通り、塩化ビニール樹脂などを主な原料とした壁紙のことで日本の多くの住宅で使用されています。
ビニールという素材は加工がしやすく、凹凸のあるエンボス加工や木目調や石目調などのプリント柄、そしてカラーバリエーションも豊富なのが特徴です。
ビニールクロスは内装仕上げ材の中でも大量生産ができ値段も安いため、家づくりの際に標準仕様の壁紙として使われることが多いです。
耐久性が高いということもビニールクロスの特徴でもあります。摩擦や衝撃にも強く汚れもつきにくいため掃除もしやすいです。水や湿気にも強いためキッチンや洗面所、トイレなど水回りに適しています。しかし、経年劣化をするので10年ほどで張り替えが必要になります。
ビニールクロスは施工しやすいのも特徴で、DIYで壁紙を貼ることも可能です。
紙クロスとは
紙クロスとはパルプや和紙、再生紙などの紙を主原料として作られた壁紙のことです。紙クロスはビニールクロスより施工の手間が2~3倍ほどかかりますが、自然素材ならではの通気性や、風合いなど柔らかい印象があるのが特徴です。
紙クロスは種類も豊富で、和紙など日本の伝統的なものもあれば、アメリカやヨーロッパなど海外からの輸入壁紙もあり、デザインも多々あります。
しかし、水に弱くシミになりやすいというデメリットがあるため、クロスを貼る場所は水回りは避けるなど注意が必要です。
織物クロスとは
織物クロスは木綿や麻など天然素材の糸と糸を織り込んで作った物で、布クロスとも呼ばれています。また、ポリエステルやレーヨンなどの化学繊維を織り込んだ布に紙を裏打ちして作った壁紙の事も織物クロスの種類に入ります。
天然素材の織物クロスは、ビニールクロスとは違い、通気性や調湿性があるため結露の発生を抑え、お部屋の中を快適な環境に保つ効果も期待できます。
さらに織物クロスは、洋服と同じく布を原料としているため、紙やビニールクロスに比べ破れにくく耐久性があります。
デザインはビニールクロスほど多くはないですが、糸と糸の織り方や織物ならではの凹凸や奥行き、風合いが美しくホテルや旅館、美術館などでも使用され、プリントでは表現できない高級感も演出してくれます。
さらに、自然素材を使用している織物クロスは、化学物質が不安というお子さんがいるご家庭やアレルギーのある方にも向いています。
アトピッコハウスには「すっぴんクロス」という織物クロスがあり、糸の種類や織り方で10種類のバリエーションをご用意しています。素手では破れないほど丈夫で、経年美化をするため20年は張り替えが不要です。
▶種類が豊富で美しいアトピッコハウスの自然素材の壁紙「すっぴんクロス」の詳細はこちらからご覧ください。
クロスの貼り方は種類によって変わる

もし、DIYで壁紙クロスの施工を考えているのであれば、
ホームセンター等で売っている、
始めから、裏側に「糊」がついた壁紙を
選んだ方がいいと思います。
ただし、最初から「糊」がついた壁紙は、
ビニールクロスしかないと思います。
DIY初心者で、素材も気にならない方は、
簡単に施工ができる、のり付き壁紙を選ぶのがおすすめです。
ここからは、壁紙の裏面の種類と、種類によっての貼り方を詳しく解説します。
アトピッコハウスの「すっぴんクロス」は、本物の織物壁紙で、
「のり」もついていないので、DIYは出来ません。
ただし、吸音性・調湿性があり、メンテナンス不要です。
▶「すっぴんクロス」は全10色のバリエーションがあるアトピッコハウスの自然素材の織物クロスです。詳細は、こちらをご覧ください
クロスの種類1 のり無し壁紙
のり無し壁紙というのは、その名の通り壁紙の裏面に糊がついていない壁紙のことを指しています。DIYで壁紙を貼る際は自分で後から接着剤を付けるため、乾燥を気にせず自分のペースでDIY作業を進める事ができます。
糊を付ける方法としては専用の刷毛やローラーで付けていきます。
のり無し壁紙は施工方法の自由度が高いこともメリットで、のりではなく、マスキングテープの上から両面テープを使用して貼れば、賃貸物件でも退居時に綺麗にはがすこともできます。
のり無し壁紙は壁だけではなく、家具のリメイクや小物作りなど様々な用途でも活用でき、生のり付き壁紙より値段も安く購入できます。
クロスの種類2 生のり付き壁紙
生のり付き壁紙は、最初から壁紙の裏に貼る用の糊が塗られている壁紙の事で、フィルムを剥がすだけで簡単に貼る事ができるため、DIY向けの壁紙です。糊付けはDIY初心者には難しいため手軽に壁紙を貼り替えたい、リフォームしたいという方におすすめの壁紙です。
生のり付き壁紙はのりが完全に乾くまで貼り直しが可能ですが、保存期間は2~3週間ほどなので商品が到着してからなるべく早めに施工作業をする必要があります。
そして、生のり付き壁紙は強力な糊がついているため、剥がす際に下地を傷つけてしまうことがあったり、うまく剥がすことが難しいため原状回復が必要な賃貸物件には向いていません。
クロスの種類3 シールタイプの壁紙
シールタイプの壁紙は壁紙の裏面にシールが貼ってあり、剥離紙を剥がすだけで貼れる壁紙です。そのため、接着剤が不要のためコストも抑えられます。
シールタイプの壁紙を貼る際は裏面のシールを剥がすだけなので、DIY初心者さんにも手軽に使用することができます。剥がしやすいタイプの物は賃貸物件にも向いており、模様替えやお部屋の雰囲気を変えたいときに最適です。
シールタイプの壁紙には、既存の壁紙の上から貼ることもできるタイプもあります。
クロスの貼り方~道具を準備しよう~
ホームセンターやネットショップの他、100円均一でも
壁紙を購入することができます。
前述でも解説しましたが、壁紙クロスは大きく分けると、
「生のり付き」「のりなし」「シールタイプ」があります。
施工方法を確認し、自分が無理なくDIY施工できる商品を選びましょう。
クロスを選んだら、必要な道具を用意しましょう。
クロス貼りで用意したい道具
・バケツ・・・糊を使用する際に糊を入れておきます
・雑巾・・・余分な糊や水分を拭き取る際に使用します
・脚立・・・高いところでの作業に役立ちます
・メジャー・・・壁紙を貼る位置や壁の幅を測るのに使用します
・ステンレス地ベラ・・・カッターで壁紙をカットする際に定規の役割を果たし、壁紙を真っ直ぐ切るのに役立ちます
・ハケ・・・糊付けをしたり、壁紙を貼ったあとに空気を抜いたり、しわを伸ばすのに使います
・ジョイントローラー・・・壁紙のつなぎ目や四隅を埋めるために使用します
・カッター・・・壁紙をカットするのに使用します
・ジョイントコーク・・・壁紙の隙間を埋めるために使用します
・ヘラ・・・壁紙のしわを伸ばしたり、空気を抜いたりする際に使用します
ローラーやハケなど、クロス貼りキットとしてまとめて販売しているので、
セット商品が便利かもしれません。

クロスの貼り方~下準備~
1.面積を測り、必要数量を算出する。
壁紙を貼りたい場所の縦と横を測ります。
壁紙の幅を90cmと計算して、お部屋の天井から床までの高さから窓や扉の高さを除いた長さ+5cmをカッターで切り出します。
5cmは切りしろで、天井の場合は10cm程度余裕を持っておくと良いです。
柄やデザインのある壁紙の場合は柄合わせという作業が必要になるためロス率がさらに高くなる点にも注意してください。
壁紙はメートル単位で販売していることが多いです。
必要数量を確認し、準備しましょう。
2.壁を平らな状態にする。障害物は取り除く。
外せる部分は、できる限り取り除くと作業が楽になります。
・カーテンレール
・コンセントカバー
・スイッチプレート
エアコンなど動かしにくいものは、シートなどで養生をしておきましょう。
3.クロスをはがす
今貼っているクロスをはがすか、そのままにするかによって、工程が変わります。
シートタイプの壁紙の場合、既存壁紙の上に貼れますが、
糊付き、糊なしクロスに張り替える場合は、古いクロスをはがす必要があります。
◆クロスをはがさない場合◆
クロスの表面の色が黒ずんでいたら、汚れを落としておきましょう。
はがれがある部分は、壁紙用の補修糊で補修しておくとよいでしょう。
◆クロスをはがす場合◆
既存の壁紙の継ぎ目がはっきりわかる場合、そこからめくると簡単です。
継ぎ目が見つからない場合は、壁紙の表面を切ってそこから剥がします。
剥がすと、薄い裏紙が壁に張り付いて残りますが、
裏紙はできる限り、きれいに残しましょう。
4.下地処理をする
下地処理とは、クロスを貼る前に一度まっ平らな状態を作る工程です。
仮に、穴が開いていたり亀裂があれば、補修用テープやパテで補修をします。
クロスをはがした場合、裏紙が残りますが、
裏紙がきれいに残っている部分と、下地が露出している部分がある場合、
多少の段差がありますので、
シーラーやパテを全体的に塗り、裏紙を固定したり段差をなくす処理をします。
ここからは、クロスの種類ごとにクロスの貼り方を解説します。
すっぴんクロスは、本物の織物壁紙で、DIY不可ですが、
ここまでの施工手順は、一般的なクロスと同じです。
▶アトピッコハウスの織物クロス「すっぴんクロス」の詳細を知りたい方は、こちら
生のり付きクロスの貼り方
先ほどもご紹介しましたが、改めて生のり付きクロスとはなにか?
あらかじめ、クロス裏にのりが塗布されていて、のりが乾かないように
フィルムが張られている商品です。
壁紙の両端には端からのりが乾くのを防ぐため、左右色が違うビニールテープが挟み込まれています。
左右でテープの色が違うのは、折りたたんだ状態でも貼り付ける左右を分かりやすくするためです。
フィルム部分には目盛りがついているので、
必要な分だけカットできます。
エアコン周り、窓周りはクロスを何枚か貼り合わせて施工します。
クロスを張ったら、最後にハケで空気を押し出し、地ベラをあてて、上下の余分をカッターでカットします。
カッターの角度はなるべく寝かせて持ち、こまめにカッターの刃を折って使いましょう。

のりなしクロスの貼り方
のりなしクロスは、壁紙用糊を用意して、
のりつけ機などで、糊を付着させた状態にする必要があります。
初心者でのりなしクロスは難易度が高いと言えます。

薄手の壁紙の場合は、両面テープでもはることができるので、
DIYでも可能です。
賃貸の場合は、マスキングテープの上に、両面テープを貼り、
クロスを施工する方法があり、気軽にイメージを変えることができ、
原状回復もしやすいです。
すっぴんクロスは、本物の織物壁紙ですが、のり付け機は、使えます。
DIYだと難易度が高いですが、施工性はビニールクロスとさほど変わりません。
自然素材クロスの貼り方
自然素材系の壁紙クロスは、
貼る直前に「糊」を付けないと、
「アイハギ」という現象が起きて、使い物にならなくなります。
アイハギとは、糊を付けた「裏紙」同士が付着して、
剥がれなくなることを言います。
一旦アイハギを起こしてしまうと、もう使い物にならなくなりますので、
15分以上放置することは避けましょう。
織物クロスは、厚手なのでジョイントが目立たないように、
突きつけ張りで貼ります。
丁寧な作業が必要なので、DIYは難易度が高いです。プロに依頼しましょう。
すっぴんクロスも、まさに本物の織物壁紙です。
DIYは難しいので綺麗に仕上げるためにも工事はプロに依頼しましょう。
▶すっぴんクロスの施工方法は、こちらで詳しくご紹介しています
クロスの貼り方~継ぎ目処理の仕方~
市販されている壁紙クロスは、
有効幅が90cmとか、92cmになっていて、
製品そのものの幅は、95cmとか、98cmの種類があります。
施工方法は、
「相裁ち」か「突き付け」かを選択することになります。
●相裁ち
90cm幅のものを貼り継いで行く際に、
1枚目と2枚目の「端」を少し重ねてカットすることで、
壁紙クロスのジョイントを処理する方法です。
長所は、継ぎ目がピッタリと合うことなので、
柄物クロスの場合は、相裁ちで施工することが多いです。
欠点は、下地の石膏ボートの表面紙までカットしてしまう
恐れがあります。その場合、いずれジョイント部分が剥がれて
きてしまうのです。
●突き付け
90cm幅のものを貼り継いで行く際、
「端」を重ねないで前の壁紙クロスに、
ピッタリ合うように次の壁紙クロスを「突き付ける」方法です。
この方法は、壁の上で、壁紙クロスをカットしないので、
下地の石膏ボードを傷つけることがありません。
従って長所としては、カットが原因で、
ジョイントから剥がれてくることがないということです。
しかし、欠点としては、
腕が悪かったり、工事が雑だったりすると、
壁紙クロスのジョイントに、
「隙間」が出来てしまうのです。
クロスの貼り方は継ぎ目部分が大事です。
継ぎ目が目立ってしまうと、部屋の印象も崩れます。
アトピッコハウスの「すっぴんクロス」詳しいの施工方法は、突き付け貼りが基本です。
クロスの貼り方~入隅出隅の処理の仕方~
部屋には、入隅と出隅という部分があります。
簡単に作業するなら、入隅はそれぞれの壁面でカットしたものを貼りますが、
クロスの収縮で隙間が目立ってきます。
入隅の隙間を目立たなくするには、
壁紙をカットせず連続して、
壁紙を折り曲げながら貼る必要があります。
特に難しい作業ではないですが、
後々はがれてこないように丁寧な作業が必要です。
クロスの貼り方~コンセント部分~
壁紙を貼る前にコンセントカバーを外します。カバーを外すとパネルが出てきますのでそのパネルも外します。
カバーの内側まで壁紙を貼ることで際まで壁紙を貼ることができ、仕上がりがキレイです。
壁紙を貼る際には一度コンセントに壁紙をかぶせ、コンセントの位置を確認したのち、カッターでコンセント部分をカットします。
カッターでコンセントをキズつけないように壁紙を浮かせてカットするようにしましょう。
これをマスターすればインターホンなど、壁に設置されている障害物はほとんど対応できます。
クロスの貼り方~窓回り~
壁紙を窓に貼る際の張り方も窓にかぶせるように壁紙を貼っていき、窓枠をキズつけないように壁紙を浮かせながらカッターやハサミでカットしていきます。竹べらでなぞり、余分な部分に折り目を付け、地ベラをあててカッターで余分な分をカットします。
クロスの貼り方~天井~
重力に逆らって施工をする天井の壁紙はDIYではなかなかハードルが高いですが、足場をしっかり組み、壁紙が落ちてこないよう糊を通常の2倍ほどたっぷりつけ、可能であれば二人がかりで対応すればDIYでの天井の施工も可能です。
クロスがめくれたり穴が空いてしまった!?壁紙の補修方法とは?
貼ったクロスの一部がめくれてしまったり、穴が空いてしまった際には軽度なものであれば壁紙補修材などを使って自分で補修することが可能です。ここからは起こりうるそれぞれの補修方法をご紹介します。
クロスがめくれてしまった際の補修方法
クロスがめくれたり、剥がれてしまった際には、壁紙補修用の接着剤で貼り直すことが可能です。
まず、壁紙の剥がれやめくれた部分の裏面や壁の周りに付いている古い接着剤を布や雑巾で綺麗に拭き取ります。きれいに拭き取る事で新しい接着剤の付きをよくしてくれます。
そして、剥がれやめくれた部分に応じた量の接着剤をヘラなどで塗り、壁紙を貼りつけます。その際空気をしっかりと押し出しながら貼るのがポイントです。
クロスに小さい穴が空いてしまった際の補修方法
画鋲などの5ミリ程度の小さい穴が空いてしまった際は比較的簡単に補修することができます。
まず壁紙の色に近い穴埋め材を穴に塗ります。その際少し盛り上がる様に塗るのがポイントで、その後ヘラを使って盛り上がった穴埋め材を周りの壁と馴染むように平らにしていきます。
穴埋め材の乾燥後、必要に応じてまた補修材を塗ったり、サンドペーパーなどで表面をなめらかにしたり塗装したりしましょう。
クロスに中くらいの穴が空いてしまった際の補修方法
1㎝から握りこぶし程の中くらいの穴が空いてしまった際は、まずは新しいクロスと壁の補修用のパテ、そしてリペアプレートを用意しましょう。リペアプレートとは、粘着剤付きのグラスファイバーテープにアルミ板が合わさったもので貼るだけで壁に空いた穴の補修ができます。
補修の手順としては、まず空いてしまった穴の周りの壁を四角くカットし剝がします。そして、石膏ボードの下地にリペアプレートを穴がしっかり覆われるように貼ります。
その後、リペアプレートの上から壁の下地用のパテを塗り平にしていきましょう。そしてパテが乾燥したら新しいクロスを貼ります。
クロスに大きい穴が空いてしまった際の補修方法
握りこぶし(約10㎝)から20㎝程度の穴でしたら、上記の方法で壁の補修がDIYでも可能です。
しかし、20㎝以上の大きな穴になるとなかなかDIYでは補修をするのが難しい場合があります。さらに、壁の内部にある石膏ボードが大きく破損している場合も下地からしっかり補修しなくてはならないので、専門業者などプロに頼むのが安心です。
補修費用は穴の大きさや破損の度合いによっても変わりますが、20㎝以上の穴だと30000円~50000円くらいが相場と言えます。
小さい穴でも見た目を元のようにしっかり戻したいという場合も、DIYより専門業者に施工をお願いするのがおすすめです。
DIYでも張りやすいクロスの選び方、張り方
DIYでも簡単で張りやすい壁紙は糊付きやシールタイプの壁紙です。さらに柄付きの物だと柄を合わせるのが難しいので初心者には無地の壁紙をおすすめします。また、小さな場所から始めてコツをつかんでみる、2人以上で作業をするなどするとDIYでの壁紙もやりやすいでしょう。
いずれにしてもカッターの刃はこまめに変えて切れ味を良くしておくことがポイントです。
YouTubeなどでも壁紙DIY向けのの下地処理から色柄の合わせ方のコツ、必要な道具の紹介などを見ることができるのでチェックしてみるのもおすすめです。
まとめ
今回は壁紙をDIYで貼る際に知って欲しいことや貼り方についてご紹介しましたがいかがでしたか?
初めて壁紙をDIYで施工する場合、
のり無し壁紙ではなく、のりつき壁紙やシール付きタイプの壁紙を選ぶといいと思います。
下地を問わず、コツのいらない100均などで売っている
シールタイプの壁紙を購入してみて戸棚など簡単な場所からスタートしてみるのも
おすすめです。
是非自分の好きな壁紙を見つけ、自分好みのお部屋にDIYしてみてくださいね。
アトピッコハウスの「すっぴんクロス」は、自然素材の
織物壁紙(布クロス)です。
吸音性、耐久性に優れた織物クロスは、
長い年月使うことができます。
ビニールクロスのように経年劣化せず、経年美化で20年は貼り替えが不要です。
DIY施工はできませんので、「すっぴんクロス」を張るのはプロにお任せくださいね。
▶アトピッコハウスの丈夫で耐久性に優れた織物クロス「すっぴんクロス」は経年変化が美しい壁紙です。資料をご希望の方は、こちらからどうぞ!
よくあるご質問
織物クロスのメリットは?
アトピッコハウスの織物クロス「すっぴんクロス」は、綿や麻などの糸と糸を織り上げた織物に裏紙をつけた壁紙です。地震や近隣工事で発生する振動にも伸縮して動きについていけるため、破れにくく耐久性が高い壁紙です。そのため、張り替えの回数が少なくてすむので、その分ビニールクロスよりコストパフォーマンスがよいといえます。そして、自然素材の織物クロスは調湿性や通気性もあるため、結露を抑えお部屋の中を快適な状態に保ってくれます。
さらに「すっぴんクロス」は吸音性が高いため、防音室の壁紙に採用される方もいます。
織物クロスのメンテナンス方法は?
アトピッコハウスの織物クロス「すっぴんクロス」は、静電気が発生しにくいため、ホコリなどは付きにくく、基本的にノーメンテナンスでOKです。鉛筆などの汚れはきれいな消しゴムで擦ると取ることができ、ホコリや泥などはガムテープなどでぺたぺたすると取ることができます。壁紙にお醤油など濃い液体を付着してしまった場合、シミになりますが、ゴシゴシと水拭きは不可です。壁紙に汚れがなじんでいくのを待つか、張替えリフォームが必要です。
クロス貼りは、どこから始めればいい?
壁の角や柱は垂直だと思われがちですが、垂直でない場合がありますので、壁紙の貼り始めは壁の端ではなく真ん中からがおすすめ。糸に重りをつけて正確に垂直に測り、壁の正面に立ち、壁紙のメインになる模様が目線の位置に来るよう高さを調整します。
クロスの張替えは、何日かかるの?
壁紙の張替えはお部屋の広さや、張り替えるクロスの種類などでも変わりますが、大体1日から1日半くらいで完了します。早い場合は半日で終了します。
壁に傷があったり、下地が劣化していたりすると下地補修が必要なため2日以上かかることもあります。さらに、布クロスなど丁寧な施工が必要な場合も、2日程度かかる場合があります。そのため、スムーズに作業を進めるためにも事前に施工業者に下地の状態を確認してもらうなどをしておくと安心です。
無料で、資料・サンプル差し上げます
アトピッコハウスは、無垢・珪藻土・漆喰・クロス・畳など
オリジナルの自然素材内装材を、製造販売する会社です。