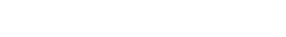日本の生活に合った塗り壁の調湿効果を解説
「梅雨どきのジメジメが気になる…」「日本では結露やダニ、カビの繁殖はあきらめるしかない…」「冬は乾燥で喉がイガイガする…」そんなお悩みを抱える方におすすめしたいのが、“塗り壁の調湿効果”です。
日本には季節があり、夏は高温多湿、冬は気温が低下し、乾燥するという過酷な環境下での生活となっています。
そんな季節が移ろう日本の環境下でおすすめなのが調湿する材料を内装に使用するということ。
自然素材を使った塗り壁には、室内の湿度をコントロールする力があります。湿度が高いときは余分な水分を吸い取り、乾燥しているときには蓄えた湿気を少しずつ放出。まるで呼吸するように室内環境を整えてくれるのです。
今回は、そんな塗り壁がもたらす調湿効果について、仕組みやメリットをわかりやすくご紹介していきます。
アトピッコハウスの珪藻土塗り壁「はいから小町」は業界トップクラスの調湿機能を誇ります
目次
塗り壁の調湿効果とは

自然素材の内装材専門メーカー、アトピッコハウス内藤です。
夏は高温多湿で、冬は乾燥する日本で、やっぱり気になるのは、湿度です。湿度が高いと、カビやダニが発生、繁殖し、人にも住宅にも健康被害のリスクが高まります。
昔の家は、土壁に、無垢材の建材の床、和室には畳に障子にふすまと自然素材で作られていたため、何もせずに家自体が調湿してくれるという作りでした。木材の建具は動くし、障子の窓など隙間風が入るし、何よりも夏の湿度と暑さに対策された家づくりだったため、風通しの良い間取りの設計がされていました。そもそもの家の造りが調湿機能を持ち、快適な環境にできるような設計がなされていたというわけです。

現代の住宅は気密性が高いです。そのため、隙間風など起こることもなく、部屋を閉め切った状態では空気の動きはほとんどありません。空気が澱むことでさらに、カビの発生やダニの繁殖などのリスクが高まります。
内装がビニールの壁や接着剤固めた木材床など、調湿機能をもたない建材を使用することでさらに密閉された空間になってしまいます。
調湿機能とは、湿気を吸って、吐くという効果です。調湿というと夏場のジメジメした時期に部屋の湿気を吸い取ってくれるということはご存知の方も多いと思いますが、塗り壁の調湿機能には吸うだけではなく、吐き出す能力もあるんです。 夏場にはジメッとした湿度を吸ってくれ、冬場の乾燥したいには蓄えた湿度を吐き出してくれるという特性を持っています。
吸うだけでは調湿とは言えません。吐き出すことも含めて調湿効果と呼ぶことができるというところがポイントです。湿度を適切に調整することで、健康面、生活のしやすさ、家の寿命においてメリットがあります。
湿度が40〜60%程度に保たれていると、風邪やインフルエンザなどのウイルスが活性化しにくくなり、のどや肌の乾燥リスクも防げます。また、アレルギーの原因となるカビやダニの繁殖、ホコリの発生リスクを抑えることにもつながります。
さらに、室内の湿度が安定していると、体感温度が穏やかになり、冬は暖かく、夏は涼しく感じやすくなります。室内干しの洗濯物の乾き具合や、室内の空気感など、暮らしの快適さも大きく左右されます。
また、家の寿命を長くさせるという点でも湿度管理は重要です。湿気が多すぎると湿度や結露によりシロアリやカビ、ダニなどが発生、繁殖し、健康へのリスクだけでなく、家や建材の寿命にも影響していきます。塗り壁や畳、無垢材といった自然素材の調湿性能を活かすことで、住まいをより快適で健やかな空間に保つことができます。
このように、湿度をコントロールすることは、人の健康と快適な暮らし、そして住まいの健全さを守るうえで欠かせない重要なポイントと言えます。
アトピッコハウスには、「はいから小町」という珪藻土塗り壁がありますが、こちらの調湿効果は、JIS規格の3倍、一般的な漆喰の6倍以上。241g/㎡/24hです。
調湿性能の効果はどのくらい続くの?
調湿機能とは、室内の湿度が高いときは吸い、低いときは吐く、ということ。このような呼吸の量がJIS規格の定める規定をクリアすると、「調湿建材」と謳えるのです。
でも、実際の調湿性能の効果はどのくらい続くの?こういったご質問、時折見かけますが、結論から言うと、何十年と持ちます。
自然素材は当たり前ですが、自然のものからできた素材です。自然のものにはそれぞれ細胞があり、その一つ一つが呼吸をするため、建材となった後も調湿性能の恩恵を受けられるのです。
その呼吸は半永久的に行われるため、調湿性能も半永久的に続くというわけです。
ただし、私たちが閉め切った部屋で換気もせずに過ごすと空気が澱んで息苦しく感じるのと同様、調湿する建材も新鮮な空気が必須になります。

難しいことではありません。窓を開けて空気を入れ替えて換気をする。それだけです。1日中24時間換気をするよりも、1日に数回窓を開けて換気をすることがポイントです。新鮮な空気を室内に取り入れることは私たちの健康だけでなく、住宅の寿命にも影響してきます。それだけで室内環境が良くなるなんて意外に手軽だと思いませんか?
アトピッコハウスの珪藻土塗り壁「はいから小町」は高い調湿性能で室内を快適にします
▶調湿効果の高い珪藻土塗り壁「はいから小町」はこちら
本漆喰が調湿したのは土壁との組合わせ
アトピッコハウスでも、珪藻土塗り壁はいから小町の調湿性能を気に入って資料請求を頂くことが多いです。
現代では調湿性能と言えば珪藻土という認識が広まっていますが、元々昔からの塗壁の代表といえば、本漆喰です。漆喰にも調湿性能があるといった情報も見かけますが実はこれ、漆喰が塗られている下の壁が土壁だった頃のお話なんです。
土壁自体が呼吸をしますから、その呼吸を阻害しない漆喰を上から塗ることで、調湿機能が維持されていました。「漆喰は調湿してくれる」という方程式はこうして出来上がったのです。実際は本漆喰にはほとんど調湿作用はなく、調湿効果をもたらしていたのは土壁だったというわけです。
しかし現在の住宅では土壁は現実的ではありません。施工ができる職人さんも少なく、木造建築、鉄筋建築、新築、リフォームにかかわらず、ほとんどの壁は石膏ボード下地になります。石膏ボードの下にはセルロースファイバーなどの断熱材が張られており、気密性が高く、現代のニーズに適していますが、外部との空気の流れをシャットアウトするというメリットの代わりに、室内の湿気がこもってしまうわけです。
ただでさえ気密性が高い建物の構造に、ビニールのクロスを貼ればそれは結露するし、カビも生えるということはご理解いただけるのではないでしょうか。
アトピッコハウスの「はいから小町」の調湿性能は、241g/㎡/24h。JIS規格の最低基準が、70g/㎡/24hなので、調湿効果は、JIS規格の3倍以上ということですね!
▶JIS規格の3倍調湿する珪藻土塗り壁「はいから小町」の詳細は、こちら
調湿効果が高い塗壁は珪藻土
ここで問われるのが、室内の壁に、厚さ2㎜程度で塗られる塗り壁材そのものの調湿性能です。本漆喰自体の調湿性能はあまり無いので、下地が石膏ボードだと調湿効果は期待できません。
調湿性能がいい塗り壁と言えば、珪藻土やゼオライトを使った塗り壁が代表的ですが、ここでは珪藻土塗り壁のお話をさせていただきます。ネットで検索すると、たくさんの珪藻土塗壁商品や材料があるかと思います。
はいから小町はそこまで名は知られていませんが、是非、こちらのグラフで比較してください。
はいから小町の調湿性能
アトピッコハウスの珪藻土塗り壁はいから小町の調湿性能は、1㎡当たり241gです。きっと他社さんでも、同じようなグラフを提示されていることかと思います。ちなみに、先ほど述べたJIS規格が定めた調湿建材の規格は、1㎡当たり70g。そうなんです、なんとJIS規格の3倍以上あるのです。
はいから小町の調湿性能の高さのポイントは、珪藻土を固める方法にあります。漆喰は置いておけばそのまま固まりますが、珪藻土は自分だけで固まることができません。
そのため、珪藻土を使用した商品には必ず凝固材が入るのですが、安い商品などでは、接着剤等で固めることが多いです。
そもそも珪藻土は珪藻という藻の化石が原料です。藻の化石には多数の小さな穴が開いていて、そこに湿気やニオイ、などを取り込んで調湿、消臭してくれるというメカニズムになります。つまり、珪藻土が持つ多孔をいかに生かすかで高い調湿性能を実現できるというわけです。
安い珪藻土などは凝固成分に接着剤を使っています。接着剤はせっかくの珪藻土の多孔をふさいでしまうので、調湿性能が期待できないものが多いです。
はいから小町の凝固方法はお豆腐のにがりと胃薬にも使われるマグネシアを使ったもので、ケミカルなものは使っていないため高い調湿性能を実現することができます。
アトピッコハウスの珪藻土塗り壁「はいから小町」は、吸湿効果も放湿効果も業界最高水準です。
はいから小町を全体に塗れば冷房不要!?
アトピッコハウスの事務所内にははいから小町が壁、天井の全面に塗られています。移転する前の以前の事務所には冷房がありませんでしたが、はいから小町のおかげで乗り切ることができていました。
時代が変わり、現在はエアコンがない状態では命に関わる暑さとなっています。はいから小町を全面に塗ったとしてもエアコンなく夏を越せるかというとそれは現実的ではありません。
アトピッコハウスがある鎌倉は湿度が、本当にすごいです。前方を海に、後方を山に囲まれていますから、町全体がモワッとこもってます。湿気や結露、カビの悩みは鎌倉あるあるです。
エアコンなしで過ごすことは難しいですが、調湿してくれる珪藻土塗り壁のおかげで、空調の設定温度は27℃でも快適に過ごせています。湿度を下げれば体感温度が下がります。何より不快なのは、湿度。これを壁が勝手に吸ってくれるのは本当に助かりますね!

「でも、吸い切っちゃったら効果がなくなっちゃうの?」
いいえ、大丈夫です。
吸うだけなのは、吸湿・除湿です。調湿とは、湿度を吸って吐くということ。湿度が低いときには、吸った湿気を吐きます。吸いすぎて効果が数年しかもたないなんてことは、ありえないのです。
ただし、せっかく珪藻土を選ばれるのであれば広い面積での施工をおすすめしたいです。
除湿機器と違い、自然素材は呼吸します。除湿機器と違い、壊れることもありません。はいから小町は、半永久的に大きく呼吸をしてくれます。20年、30年と呼吸をし続けてくれる壁に囲まれて毎日快適に過ごせたら、とても幸せですね!
▶調湿性能の高い珪藻土塗り壁「はいから小町」の詳細は、こちら
こんなものも調湿効果のある素材
木材である無垢材は調湿効果がある
塗り壁に調湿効果があることはお伝えしましたが実は、それだけではありません。床や壁に使われる「木材」、とくに自然のままの状態で使われる「無垢材」にも、優れた調湿効果があるのです。

無垢材といえば、ヒノキやスギ、ナラなど、昔から日本の家づくりに使われてきた木材が思い浮かぶでしょう。床材としてだけでなく、梁や柱といった構造材にも幅広く使われています。こういった木材は、空気中の湿度が高くなると余分な水分を吸収し、乾燥してくると蓄えていた水分を放出する、まさに「呼吸する素材」です。人が気づかないうちに、室内の湿度を緩やかに整えてくれているのです。
無垢材は、古くから日本の暮らしの中に溶け込み、快適な住まいを支えてきました。現代のように空調設備が発達していなかった時代でも、人々は自然の素材を上手に取り入れながら、心地よい空間を作ってきたのです。
最近では、竹炭のような調湿性に優れた素材にも注目が集まっていますが、こうした昔ながらの無垢材の力をあらためて見直すことも、より健康的な住まいづくりには欠かせないことかもしれません。
調湿効果のある壁紙は布クロスや紙クロス
調湿効果といえば、塗り壁や無垢材が代表的ですが、実は壁紙の中にも湿度をコントロールする性質をもつものがあります。その代表が、布クロスや紙クロスといった自然素材の壁紙です。
これらの壁紙は、ビニールクロスと違って表面が自然素材でできているため、空気中の湿気をある程度吸収したり放出したりすることができます。そのため、塗り壁ほど強い効果ではないにせよ、室内の湿度を緩やかに調整し、結露やカビの発生を抑える助けになります。
特に和紙を使用した紙クロスや、リネンやコットンなどの天然素材を使用した布クロスは、調湿性能だけでなく見た目の温かみや質感が魅力でどんなインテリアにも合い、時間が経っても楽しめます。
塗り壁の方が調湿機能は高いですが、広い面積である壁や天井に自然素材の材料を施工することで、カビや結露のリスクの低下に役立ちます。
床下には木炭やセルロースファイバーで調湿効果を高める
床下の環境は、見えない部分ではありますが、住まい全体の快適さや耐久性に大きな影響を与える重要な部分です。特に湿気がこもりやすい床下は、カビやシロアリの発生リスクが高まるため、調湿対策は必須です。そこで効果を発揮するのが、木炭やセルロースファイバーといった自然素材を使った調湿方法です。
まず、木炭は古くから知られる調湿材で、非常に多くの微細な孔(あな)を持っているため、空気中の湿気を吸収したり放出したりする働きがあります。さらに、消臭効果や有害物質の吸着といった効果もあり、床下に敷き詰めることで湿気を安定させ、清潔で快適な住環境を保つ手助けをしてくれます。

一方、セルロースファイバーは、新聞紙などを原料にした自然由来の断熱材ですが、調湿機能も兼ね備えています。湿気を一時的に吸収して蓄え、必要に応じて放出する「可変透湿性」があるため、床下に限らず壁や天井にも使用されます。特に、断熱材として調湿対策のできるしてセルロースファイバーを床下に使うと、断熱と調湿の両面から快適な室内環境を実現できます。
このように、床下に木炭やセルロースファイバーを活用することで、目に見えない場所から住まい全体の湿度バランスを整えることができ、建物の長寿命化や健康的な住環境づくりに大きく貢献してくれるのです。
最近では、竹炭のような調湿性に優れた素材にも注目が集まっていますが、こうした昔ながらの無垢材の力をあらためて見直すことも、より健やかな住まいづくりには欠かせない視点かもしれません。
アトピッコハウスでは無垢材や織り物クロスも扱っています。
昔から使われているものには理由がある
食べものにまつわる昔ながらの知恵を見ても、それはよくわかります。たとえば、木でできた「曲げわっぱ」や、竹の葉で包んだおにぎり。どちらも昔から親しまれてきたものですが、その理由はおいしさだけではありません。通気性がよく、余分な湿気を吸ってくれるから、食材が蒸れずに美味しさを保てるのです。

こうした自然素材が持つ「呼吸する力」は、どこか安心感を与えてくれます。観葉植物を飾ったり、木製のすのこを敷いたりと、私たちは無意識のうちに自然を暮らしに取り入れています。それは、自然素材が持つ優しさや温もりに、心がホッとするからなのかもしれません。
内装材においても、こうした自然の力を活かすことで、もっと心地よい住まいがつくれるはずです。昔から使われているものには、それなりの理由がある。今こそ、その知恵を住まいづくりにも取り入れてみませんか?
まとめ
日本の気候特有の「ジメジメ」や「乾燥」に悩まされている方は多いと思います。そんな中、注目したいのが自然素材の持つ調湿効果。とくに塗り壁や無垢材には、空気中の湿度を吸ったり吐いたりする「呼吸する力」が備わっており、室内の湿度を自然にコントロールしてくれます。
アトピッコハウスの珪藻土塗り壁「はいから小町」は、JIS規格の3倍以上という圧倒的な調湿性能を誇り、湿度が高い時期は余分な湿気を吸い取り、乾燥時にはやさしく放出。冷暖房に頼りきらない、心地よい空間をつくる手助けをしてくれます。
他にも、床に使われる無垢材や、壁紙としての布クロス・紙クロス、床下の木炭やセルロースファイバーなど、自然素材はさまざまな形で住まいの調湿に貢献しています。これらはすべて、古くから使われてきた素材たち。竹の葉に包んだおにぎりや曲げわっぱの弁当箱が美味しさを保つように、自然素材には快適さを守る力があるのです。
時代が変わっても、自然の知恵は変わらず生き続けています。私たちの暮らしにそっと寄り添ってくれる「呼吸する素材」を、住まいづくりにも取り入れて、毎日をもっと快適に、健やかに過ごしてみませんか?
珪藻土塗り壁「はいから小町」の調湿性能は、241g。一般的な漆喰の6倍の調湿性能です。
▶漆喰の6倍調湿する珪藻土塗り壁「はいから小町」の資料は、こちらからご請求ください。
よくあるご質問
塗壁にすれば何もしなくても調湿効果はある?
塗壁を塗れば終わりというわけではありません。湿気を吸って吐くことで調湿をするので、吐き出させることが必要です。吐き出させるためには新鮮な風が必要です。風に乗せて外へと排出させることで新たな調湿効果が期待できるというわけです。1日に数回、定期的に換気をすることで、塗り壁のメリットである調湿性能や消臭効果が半永久的に続いていくのです。アトピッコハウスのはいから小町は24時間で㎡辺り241gもの調湿をします。
一壁だけ塗っても調湿効果はある?
調湿効果には許容範囲があります。コップに水を入れすぎるとこぼれてしまうように、調湿する塗壁も限度があります。人が生活していく上で、湿気は必ず生じるもの。お風呂や、料理、部屋干しなどに加え、私たちが生きて呼吸するだけでも湿気は生まれます。それだけの湿気を一壁だけの塗壁で対応することは難しいと言えます。つまり、できるだけ広い面積で施工することで調湿建材の特性が生かせるというわけです。アトピッコハウスの珪藻土塗り壁はいから小町は全8色で色々なお部屋に合わせられます。
塗り壁はリフォームでも使用できるの?
塗り壁はもちろんリフォームやリノベーションでもお勧めの材料です。気密性の高いマンションは結露、カビの繁殖リスクが多いと聞きます。ただし、その部分だけ施工しても効果は感じられません。高い調湿機能を確保したいなら気になる部分だけでなく広い範囲でリフォームをすることをおすすめします。
調湿機能のある塗壁はDIYできる?
調湿効果の高い塗壁は自然素材であることが多く、ホームセンターなどで売っている、すぐに使える簡単なものに比べ、かくはんや、下地作りなど手間がかかることが多いですが、根気強くやっていけばDIYももちろん可能です。はいから小町は調湿効果抜群、DIYされる方も多い商品です。施工要領書を読みこんで適切に施工していくことが成功へのポイントになります。天井など難しい部分は壁紙にしたり、プロに施工を依頼することなども検討してもいいと思います。
無料で、資料・サンプル差し上げます
アトピッコハウスは、無垢・珪藻土・漆喰・クロス・畳など
オリジナルの自然素材内装材を、製造販売する会社です。