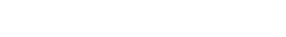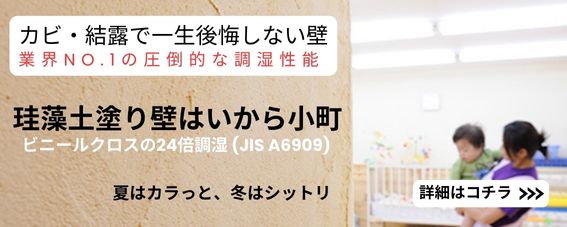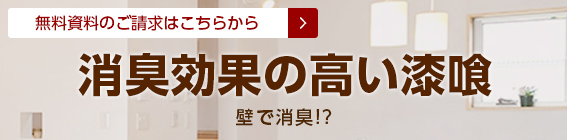竹小舞土壁とは?昔ながらの知恵とリフォームのポイント
竹小舞、読めますか?
たけこまいと読みます。
竹小舞は現代で新築される住宅では使われることはほとんどありませんが、昔ながらの日本家屋などの建築物ではまだ健在しているところも多いです。
竹小舞土壁からのリフォームを検討されている方も多いですが、新建材が多い今、なかなかハードルが高い場合があります。
また、アトピッコハウスには、珪藻土、漆喰、カオリンといった3種類のオリジナル塗り壁がありますが、竹小舞土壁への施工を、DIYで挑戦するというのは、ほぼ無理だと思います。 今回は竹小舞土壁について考えてみます。
アトピッコハウスには調湿性能が高い珪藻土塗り壁「はいから小町」があります。
目次
竹小舞土壁って知ってる?

自然素材の内装材専門メーカー、アトピッコハウスの内藤です。
竹小舞土壁とは、割った竹を縦横に組み、土台を作った壁にワラを混ぜた土を何重にも塗り重ねて作る壁のことです。
飛鳥・天平時代の公共建築や寺社建築では、小舞下地に土壁を塗る工法が広く採用されていました。
この技術は渡来人の影響によって伝えられたもので、当時の進歩的な人々の間で「新しい時代の建築」として好まれていたと考えられます。
50年ほど前までは一般的な工法として用いられてきましたが、職人仕事となりますし、手間も時間もかかるので、便利な新建材に押され、少なくなってきました。
小舞竹土壁とはどう違うの?
小舞竹(こまいだけ)とは、割った竹を細く加工し、格子状に編み込んだ竹小舞壁の下地のことをいいます。
この小舞竹にワラを混ぜた土を何度も塗り重ねて仕上げたものが「竹小舞土壁」です。つまりは竹小舞壁を作る第一段階ということですね。
構造はシンプルですが、実際には職人の技術と時間が必要で、現在は施工できる人も減ってきているといいます。
アトピッコハウスの珪藻土塗り壁「はいから小町」は竹小舞土壁には施工できませんが、調湿性能が自慢です。
竹小舞土壁のメリットとは?
竹小舞土壁のメリットはたくさんあります。まず、自然素材であること。材料である竹や土はわざわざ輸送費をかけて取り寄せなくても日本全国どこにでもある素材です。さらに、竹小舞土壁は以下のような優れた性質を持っています。
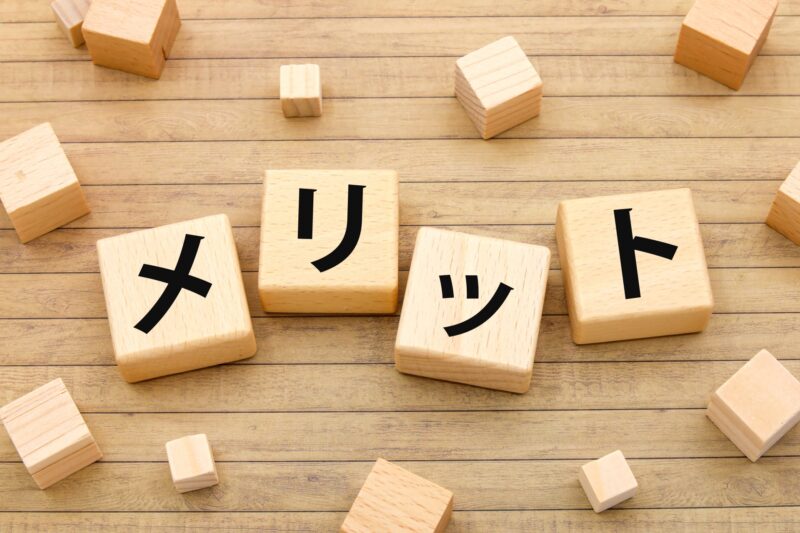
・土で覆われているため、燃えにくい・・・耐火性
・土とワラが湿気を吸収・放出し、室内の湿度を安定・・・調湿性
・しなやかな竹を組んで、土をかぶせているため柔軟性があり、崩れにくい構造・・・耐震性
・土が熱を吸収し、夏は涼しく、冬は暖かい・・・断熱性
・組んだ竹と土壁の厚みにより音が伝わりにくい・・・遮音性
また、自然素材である竹や藁縄、土を原料とした竹小舞は、役目を終えたら土に還るという、循環型の素材のため、再利用もできる環境にも優しい建材であると言えます。
昔ながらの建材には先人の知恵がたくさん詰まっていますね。
こうした特性から、かつての日本家屋では標準的に使われていました。しかし、施工に手間と時間がかかることから、残念ながら現代では新建材に取って代わられ、目にする機会が少なくなっています。
竹小舞づくりの工程
1. 竹を割る
まず、材料となる竹を選びます。節の間隔が長く、まっすぐでしなやかな竹が理想です。竹をそのまま使うのではなく、鉈やナタを使って細く割り、ヒゴ状に加工します。
割るときには竹の節を避けて裂くことで、均一な厚みの細長い部材になります。関西では丸竹が使われることが多かったようですが、丸竹よりも竹を裂いて使うことが多いようです。竹を割る技術は熟練の職人の手作業によるものが多く、力加減によって仕上がりが大きく変わる繊細な工程です。
2. 下地に編み込む
割った竹を「縦竹」と「横竹」に分け、木の骨組みに打ち付けていきます。縦竹をまず等間隔に並べ、その上に横竹を交互に通し、縄やシュロ縄でしっかりと結んで固定します。
これにより、格子状の編み込み下地(小舞)が完成します。竹のしなやかさがあるため、力が加わっても折れにくく、土を塗り込んだときの「引っ掛かり」としても機能します。小舞の組み方には地域によって違いがあり、細かく編むことでより強度を高めたり、装飾的な役割を持たせたりする場合もあります。
3. 荒壁土を塗る
小舞下地ができたら、次は「荒壁」と呼ばれる最初の土を塗ります。荒壁土は、粘土質の土に稲ワラを刻んで練り込んだものです。ワラは繊維として土をつなぎ止め、乾燥や収縮によるひび割れを防ぐ役割を果たします。
この荒壁を手や鏝(こて)で厚く塗り込み、竹の隙間にまでしっかり押し込むことで壁の骨格ができます。
塗った後は時間をかけて乾燥させますが、乾燥期間は季節や気候により数週間から数か月かかることもあり、自然素材ならではの待ち時間が必要です。
4. 中塗り・上塗り
荒壁が乾いたら、その上に「中塗り土」を施工します。中塗り土は荒壁土よりも細かい土を使い、表面を均一に整える役割を持ちます。これにより、仕上げの下地として強度と安定性が増します。
仕上げ段階では、「上塗り」として漆喰や細かい土を塗り、美しい仕上げを施します。漆喰仕上げは、白く滑らかで光を柔らかく反射し、伝統的な和の趣を生み出します。一方、土のまま仕上げると、土独特の温かみや質感を活かすことができます。
この「荒壁 → 中塗り → 上塗り」という三段階の重ね塗りにより、呼吸する壁が完成します。単なる建材ではなく、調湿・断熱・耐火といった機能を自然素材だけで実現する、日本の住まいの知恵の結晶といえます。
このように、「竹」「ワラ」「土」という身近な自然素材だけで作られているのが最大の特徴です。

竹小舞とセットで使われてきたのは漆喰
土壁と漆喰はセットで使われることが多いですが、その場合の漆喰は本漆喰です。
昔ながらの方法で作られた本漆喰との相性は抜群です。
竹小舞+土壁の組み合わせは、飛鳥時代の寺社建築から現代の町家まで使われてきました。長い年月を経てなお実例が残っていること自体が、相性の良さの実証です。
また、竹の組み方や土の塗り方には地域ごとの流儀があり、気候風土に合わせて進化してきた「職人の知恵の結晶」でもあります。
アトピッコハウスの漆喰風塗り壁「漆喰美人」は石膏ボードに塗れて土壁よりも調湿性能が高い漆喰です。
竹小舞の土壁をリフォームするには?
竹小舞土壁は「はがして張り替える」という単純な工事ができません。古い塗り壁は削り落としてから塗り直すことがほとんどですが、土壁をはがしていくと竹を編んだ竹小舞下地となり、更に外側の土壁に達するので穴が開いてしまいます。そのため、リフォームには工夫が必要になります。
しかし、現在主流となっている塗り壁は、新規ボードや石膏ボードなどを下地に塗るという前提で作られているものがほとんどです。
そのため、土壁に直接塗り壁材を塗ることはできません。水分を多く含む塗り壁を土に塗る場合、土壁が溶け、アクとして染み出してきてしまいます。
先ほどお伝えした通り、竹小舞土壁ははがすということができません。ケミカルな接着剤などで表面を一度固めるか、新規のボードに張り替えることが必要です。
石膏ボードに珪藻土塗り壁「はいから小町」で241g/㎡/24hもの調湿効果があります。
竹小舞を生かしたリフォームのメリット
クロスも塗り壁も同様ですが、基本的には土壁の上にそのまま施工することはできません。そのため、土壁を撤去して新規のボードを作る必要があります。塗り壁の場合はケミカルな接着剤などで固めてからシーラー処理など後、施工ができる場合があります。
現在では新建材が主流となり、竹小舞様式の壁を見かけることはほとんどなくなりました。しかし、日本の風土に合った竹小舞土壁は今では施工できる人も減り、希少な壁となっています。せっかくの竹小舞土壁、特性を部分的に活かすという方法もあります。
伝統的な風合いを活かせる
竹小舞と土壁の組み合わせは、日本の風土に合った伝統的な建築です。竹の細い線や編み目、土壁の微妙な凹凸が光を受けて陰影を作ることで、空間に落ち着きや深みを与えます。既存の竹小舞をそのまま残すことで、建物の歴史や職人の手仕事の跡を感じられる空間に仕上がります。新しい壁材にすべて取り換える場合と比べて、時間を経た味わいをそのまま楽しむことができるのも大きな魅力です。
環境負荷や工事コストを抑えられる
竹小舞壁を残すことで、古い下地を撤去する作業や廃材処理の手間を減らせます。建材を新たに大量に購入する必要も少なくなるため、材料費や施工費も抑えられます。
さらに、竹小舞と土壁の組み合わせは、厚みや密度により自然な断熱材の効果・調湿性を持っています。完全に撤去して新しい壁を作る場合と比べ、快適な室内環境をある程度維持できるのも利点です。
竹小舞土壁を使わなくても珪藻土塗り壁「はいから小町」なら高い調湿性能で快適な生活に!
▶241g/㎡/24hの調湿性能を誇るはいから小町の詳細はこちらから
まとめ
竹小舞土壁は、飛鳥・天平時代の寺社建築から50年前の住宅まで、幅広く用いられてきた日本の伝統工法で、割った竹を縦横に組み、ワラを混ぜた土を何度も塗り重ねて作る、日本の伝統的な内装壁です。
現在では手間と費用がかかり、新築でもリフォームでも竹小舞土壁を下地として選択する人はほとんどいません。職人仕事なので施工できる人が少ないというのも寂しい事実です。
しかし、竹小舞土壁そのものはメリットがたくさんあります。
竹小舞土壁は自然素材が原料であるため、材料となる竹や土、ワラは日本全国で手に入り、廃棄後は土に還るため環境にも優しい建材です。役目を終えたら自然に変える、再利用ができる循環型建材でもあります。
土壁で覆われていることで燃えにくく、調湿性能や、耐震性を持ち、土壁が熱を吸収することで夏は涼しく冬は暖かく過ごせるというメリットがあります。さらに竹の組み方と壁の厚みによって音も伝わりにくく、断熱性や遮音性など多くの優れた特性を持っています。
竹小舞土壁をリフォームする場合、単純にはがして塗り直すことはできないため、表面を固める工法や、新規の下地ボードに張り替えるなどの工夫が必要です。新規のボードにリフォームすれば、当社塗り壁やクロスもお使いいただけます。ぜひご検討ください。
アトピッコハウスの珪藻土塗り壁「はいから小町」は石膏ボードへの施工でも調湿性能が土壁+漆喰の6倍!
よくあるご質問
竹小舞の土壁をリフォームする方法は?
古い塗り壁ははがしてから施工することが一般的ですが、竹小舞をはがしていくと穴が開いてしまうため、新規ボードに置き換えるか、土壁部分をケミカルな接着材等で固めるという方法をとる必要があります。伝統的な竹小舞土壁は希少です。そのまま生かすという方法もあります。新規ボードに張り替えればさらに調湿性能の高い珪藻土塗り壁はいから小町への塗り替えも可能です。
竹小舞の土壁のデメリットは?
竹小舞のデメリットには、経年によりヒビが入り気密性が下がること、施工できる職人が少ないこと、施工の工程が多いため金額が高くなりがちなところがあります。土壁のため画鋲が刺さらないということがあります。アトピッコハウスの調湿塗り壁はいから小町は画鋲をさすことができます。
竹小舞の編み方は?
割った竹を「縦竹」と「横竹」に分け、木の骨組みに打ち付けていきます。縦竹をまず等間隔に並べ、その上に横竹を交互に通し、縄やシュロ縄でしっかりと結んで固定します。これにより、格子状の編み込み下地小舞が完成します。
竹小舞って削れるの?
竹小舞は削ることができません。竹と縄で組んだ小舞だけに土を塗りつけた竹小舞を削ると最終的に穴が開いて裏側まで貫通してしまうからです。竹小舞土壁をリフォームする場合は新規ボードに置き換えるか、ケミカルな材料で表面を固めるしかありません。
無料で、資料・サンプル差し上げます
アトピッコハウスは、無垢・珪藻土・漆喰・クロス・畳などオリジナルの自然素材内装材を、製造販売する会社です。