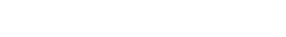マンションの遮音等級とは?防音性の高い建物の見分け方
集合住宅での生活はご近所あってのこと。自分は普通に生活をしているつもりでも、生活の仕方によって、ご近所に迷惑をかけているということもあるかもしれません。
クレームが入るほうも、クレームを入れる方も嫌な気持ちになりますし、ストレスとなります。たくさんの人が住むマンションだからこそ小さな事が大問題になりかねません。
特に騒音など音に関するトラブルはマンションなど集合住宅ではデリケートな問題になりがちです。
マンションの購入前に設備や駅からの距離、価格などだけでなく物件の構造や周辺の環境も事前に確認しておくことが大切です。
今回はマンションでの防音対策に大切な遮音等級と、防音性の高いマンションの見分け方について解説します。
アトピッコハウスでは、マンションの防音リフォームで活躍する床の遮音材「わんぱく応援マット」と言う製品を取り扱っていますが、こちらは、床の仕上げ材との組合せで、遮音性能を確保するというものです。
▶マンション床の騒音トラブルでお悩みの方におすすめな遮音材「わんぱく応援マット」の詳細は、こちら
目次
マンションの防音対策で大切な「遮音」とは?

自然素材の内装材専門メーカー、アトピッコハウスの内藤です。
マンションで防音対策をしようと色々調べていくと聴き慣れない専門用語が出てくるかと思います。その中でも「遮音(しゃおん)」という言葉は防音対策をやる上で必ず知ってほしい用語です。
遮音とは空気中に伝わる音を遮断し、外部へ漏れないようにしたり、外部の音が室内に入って来ないようにする防音方法の事を意味します。
そして防音方法は遮音だけではなく、音を吸収することで防音する「吸音」などがあります。「防音」という言葉の意味は『遮音や吸音を使って音を伝わりにくくする』仕組みのことを言います。遮音や吸音を総合して防音というのです。
床・壁・ドア・サッシの遮音等級とは?
先ほど「遮音」について解説をしましたが、この遮音性能の高さを表す指標になるのが「遮音等級」です。
マンションの防音対策を行う上でとても重要なのが「床・壁・ドア・サッシ」の遮音等級です。それぞれ「L値・Dr値・T値」と呼ばれ、日本工業規格(JIS)に基づく方法で測定された基準によりレベルが分けられます。そのため、この遮音等級をしっかり理解する事が効果的な防音対策の第一歩になります。
床の遮音等級L値とは?
「L値」は床の遮音性能を表す指標です。上階の床からの音が下階へどのくらい聞こえるかを示す数値です。Lのあとには数字が入り、この数字が小さければ小さいほど遮音性が高い事を示しています。
壁の遮音等級Dr値とは?
「Dr値」は壁の遮音性能を示す指標です。話声やテレビの音、楽器の音など、空気中に伝わる音を壁がどれくらい遮断するかを示す数値です。Dr値は数字が大きいほど遮音性能が高い事を示しています。
ドア・サッシの遮音等級T値とは?
「T値」とはドアやサッシの遮音性能を表す指標です。ドアやサッシを閉めた時にどれくらい聞こえないかを示しています。T値は「T1・T2・T3・T4」という4つの等級に分けられており、数字が大きいほど遮音性能が高くなります。
アトピッコハウスの床遮音際「わんぱく応援マット」は最大遮音等級L40 の遮音性能を持ち、マンション床の騒音対策に最適な商品です。
▶子どもやペットの足音対策にもおすすめ!「わんぱく応援マット」の詳細はこちら
マンションの建物の構造による防音性の違いを知ろう!
マンションなどの集合住宅の骨格となる部分を「構造」と言います。建物はいずれかの種類の構造により建築されています。この構造によって防音性が異なるためしっかりとチェックをしましょう。
木造
昔ながらの梁や柱を使った「在来工法」、現代の住宅の多くに使われる「2×4工法」など主な構造部分に木材を使った構造です。軽く、コストを抑えられるというメリットがある反面、木造の物件は音が伝わりやすいため防音力が低いというデメリットもあります。
アパートなど小さな物件では木造が多く、分譲マンションに比べると防音力は低いです。
鉄骨造
鉄骨造とは柱や梁などに鉄骨を使用して建てる住宅のことです。3階以上の建物には重量鉄骨を使用することが多く、2階建てまでのアパートや住宅で使われる鉄骨は軽量鉄骨がほとんどです。重量鉄骨の方が軽量鉄骨よりも防音性能は高いです。
鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造は鉄の棒で骨組みを作り、その中にコンクリートを流し固めているので強度が高く壁の密度も高いため音を伝えにくいです。
木造や鉄骨造に比べ防音力が高いため、騒音のリスクが下がります。構造は鉄筋コンクリート造を選ぶといいでしょう。構造は入居前に不動産屋さんに確認すれば分かります。
防音力の高いマンションの特徴はどこを見たらいいの?見分け方のポイント!
防音力は木造よりも鉄筋コンクリートのマンションのほうが高いです。音を通しやすい木造よりも鉄骨は音が伝わりにくいためです。防音力には、特に壁、床、窓の造りが重要となるので詳しい見分け方のポイントをご紹介します。
ポイント1:マンションの壁の遮音に関わる要因 壁の造り
お隣とつながっている壁は音が伝わりやすいということがあります。テレビを壁にくっつけていたり、お隣の寝室の壁とリビングが隣接している場合、生活環境や時間帯によってはうるさいと感じられてしまうかもしれません。
壁の厚みとしてはコンクリートが18㎝以上あるといいですが、古いマンションなどではそこまで厚みがない場合もあります。壁がコンクリートなのか、石膏ボードなのか木質なのか、仕上げの内装材によっても防音力は変わります。
壁の施工はコンクリート壁に直接クロス張りをする直壁工法と、コンクリート壁に石膏ボードを貼る二重壁(GL工法)があります。
二重壁(GL工法)は壁と石膏ボードの間の隙間の空間で音が反響してしまうこと、施工時に使われるGLボンドに音が伝わりやすいことなどから、防音性が低くなるため注意が必要です。
ポイント2:マンションの床の遮音に関わる要因 床の造り
壁と同様、音が伝わりやすい場所です。上下の住戸と直接接しているため特に足音や、椅子をひいたりする音など、音が伝わりやすく、騒音トラブルの原因になることが多い場所です。新しいマンションでは音を遮る、防音の対応をしていることがほとんどです。
床下のコンクリートスラブの厚みは270㎜程が理想ですが、古いマンションではそこまで達していないものも多いです。
ポイント3:マンションの窓の遮音に関わる要因 窓の造り
窓のサッシの隙間から外の音は入り込んできます。防音力の高い窓ガラスであっても、サッシの気密性が低ければ意味はありません。街中であれば遮音等級T-1以上、線路沿いの家の場合や幹線道路が近く車通りの多い家の場合はT-2以上のグレードのサッシがおすすめです。
ここも大事!マンションの契約前にチェックすべき事とは?
これまで防音性の高い建物の構造や壁や床などの造りについて解説をしましたが、更にマンション契約を決定する前に「ここも大事!」というポイントをご紹介します。
マンションの住戸の位置や階数選びは慎重に
生活していく上で、足音や生活音を完全に消すということは難しいです。それならば最初からリスクの少ない物件を選んだ方が騒音トラブルになりにくいです。自分が他の住人の音に悩まされたくない場合は最上階、子供やペットがいて階下の方に迷惑をかけたくないという場合は1階の部屋を選ぶといいでしょう。
また、四方を囲まれているよりも例えば角部屋のような隣接する部屋が少ない物件の方が音のリスクが少ないためおすすめです。
水回りは音が伝わりやすいため、構造や間取りの確認も必要です。そのため、マンションの寝室にトイレやバスルームが隣接している場合、給排水管を流れる水音で目が覚めてしまうなんてこともあるでしょう。リビングや寝室と水回りの間に納戸やクローゼットがある間取りの場合、音が吸収されるので防音性が高くなるためおすすめです。

遮音に関するマンションの管理規約を事前にチェックすることも大切
静かな環境のマンションで生活をしたいのなら、事前に管理組合の規約をチェックしておきましょう。マンションによってはきちんと遮音性の規約を設けているところがあります。
新しい分譲マンションでは管理組合の定める遮音性に関する決まりがあるところがほとんどですが、中古物件のマンションなどは規約が確立していない場合もあるため注意が必要です。物件を決定する前に不動産屋に確認しましょう。
リフォームするなら遮音を取る、楽器演奏は〇時まで、ペット飼育禁止などの規約があるマンションがおすすめです。音に対する管理がきちんとされているので安心です。
遮音をマンションでとるための基準とは?
そこで、集合住宅ではほとんど、防音の規定を設定しています。防音規定はJIS(日本工業規格)にもとづく方法で実験室で測定したデータから実際の現場での遮音性能を推定した遮音等級、L値で示されます。L値は上で発した音がどの程度に聞こえるかの基準として決められている遮音等級のことをいいます。
先ほども少し解説しましたが、遮音等級はL値で示され、LLはライト、軽量衝撃音を、LHはヘビー、重量衝撃音を意味します。ほとんどの物件でLHの重量衝撃音ではなく、LLの軽量衝撃音を求めていてLLの後に40や45の数字が付き、数字が小さいほど遮音性能が高いことを意味します。
LL40等級は、物の落下音などの軽音はほとんど聞こえず、上の階の気配は感じるがそう気にはならない程度。LL45等級は上の階の大きな動きは分かり、生活が多少意識される状態。
軽量衝撃音というのは、スリッパで歩く足音や、スプーンなどが落ちた時に響く音を示します。なので、騒音トラブルの原因の一因である子供の走るドタバタという音はLLには含みません。
床の遮音材「わんぱく応援マット」の遮音性能は、LLで、最大40、LHで、50です。
▶遮音性能LL40等級の床遮音材「わんぱく応援マット」は子供の足音にも効果がある防音マットです。詳細は、こちら
マンションで無垢フローリングやタイルで防音性を高めるには?
床下に空洞を作ることで防音をとる
音の問題はシビアですので、マンションなどでは騒音トラブルになることも多く、そのため管理組合が承認しないと床工事の施工に入ることができません。特にフロアタイルも無垢フローリングも防音性能がなく、音がひびきやすくなるため防音の対策が必須となります。
防音をとるのに一般的とされる方法が、コンクリートの躯体の上に防振ゴムのついた支持脚を使用し床パネルを支える床仕上げ構造で、二重床ともいいます。

二重床は支持脚により空間ができるため音が伝わりにくいというメリットがあり、二重床の段階で遮音規定をクリアできれば遮音性のない無垢フローリングやフロアタイルで仕上げることができます。反面、二重床の分の高さが出てしまうこと、また材料費、工事費ともに上がってしまうというデメリットがあります。
遮音機能一体型の床材を使って防音をとる
高さを出さないで防音できるのが遮音フローリング。フローリングとスポンジのような緩衝材が一体型となっており、厚みが出ないので、ドアなどの建具にも影響が出にくく、一体型のため遮音材や二重床の分のコストがかからないため、マンションのリフォームでは当たり前の選択肢として使われてきました。
しかし、この遮音フローリングの最大のデメリットはフカフカするというところにあります。船酔いするような、と表現される沈み込むような感触を嫌う人が増えてきました。
また、遮音のクッションが一体化しているため仕上げの床材を選べないというデメリットもあります。
遮音材単体を床下に敷き込んで防音をとる
遮音材単体の商品もあります。アトピッコハウスの「わんぱく応援マット」は現状の床材をはがして床下に敷き込むタイプの遮音材です。遮音材単体なので、仕上げ材を選ぶことができます。床下構造をする必要もないので、高さを押さえ、工事費用も抑えることができます。
▶仕上げ材との組合せで、最大L40等級の高い遮音性能を発揮する「わんぱく応援マット」の詳細は、こちら
賃貸マンションやアパートで工事をしないで遮音の対策をするには?
賃貸マンション 窓の遮音対策
マンション周辺に道路が近いなど、外からの音が気になる場合防音カーテンにするという方法があります。遮光も兼ねていることが多く、カーテンに厚みがあるため冬の寒さ対策にもなります。
遮音については一定の効果はありますがレベルは高くないので、サッシにテープを貼る、窓ガラスに遮音シートを貼るなどの対策と併用するのがおすすめです。
賃貸マンション 床の遮音対策
床を剥がして張り直すというのは大がかりな工事になります。賃貸マンションやアパートなど、簡単に工事が行えない場合は既存の床をそのままカーペットを敷いて遮音性をあげるという方法もあります。毛足の長いカーペットは音を吸収するのに効果が高いですが、掃除の大変さや衛生面でも気になるという方が多いです。
マンションやアパートでなどの賃貸では、遮音シートの代わりにホームセンターなどで購入できるジョイントマットを敷き詰めるという方法があります。ジョイントマットは自分で簡単に対策できる上、防音だけでなくこの時期には断熱効果も期待できます。汚れた場合は一枚ごと再購入できるので手軽でおすすめです。ただ、薄いので足音などのカバーはできないかもしれません。
わんぱく応援マットも既存の床の上に敷いて、その上をラグなどで覆うという方法も取れます。遮音材としての商品ですし、厚みもあるので、ジョイントマットよりも遮音に期待ができます。
賃貸マンション 壁の遮音対策
マンションやアパートは壁を隔てて部屋があり、近隣の住人が生活しています。壁と家具の隙間にウレタン素材などの吸音材を入れるという方法があります。また、壁沿いに設置するタンスや本棚に隙間なくものを入れることでさらに隣家の生活音が伝わりにくくなり、防音対策になります。
まとめ
リフォームの際にはもちろん然るべく手続きを取り、防音性能を満たすことが大切ですが、上下左右のお宅くらいは日ごろからご挨拶をかわし、ご近所づきあいをしておくということも大切な一つだと思います。
どれだけ、試験結果が出ている防音材を使おうとも、素人が見れば防音の試験結果など読み取ることはできません。それよりも、いつもうるさくしてすみませんという一言があるだけで心情は変わるのではないでしょうか。
挨拶を交わす関係を構築することで、生活もしやすくなるのだと思います。床遮音材「わんぱく応援マット」は無垢フローリングとの組み合わせでLL45等級、合板フローリングとの組み合わせでLL40等級を取得しています。床工事の際にはぜひご検討ください。
▶遮音性能L40等級の床遮音材「わんぱく応援マット」の資料は、こちらからご請求ください
よくあるご質問
マンションの遮音性の基準は?
ほとんどの物件で軽量衝撃音(LL)を求めており、LLの後につく40や45の数字が小さいほど遮音性能が高いことを意味します。LL40等級は、物の落下音などの軽音はほとんど聞こえず、上の階の気配は感じるがそう気にはならない程度。LL45等級は上の階の大きな動きは分かり、生活が多少意識される状態。床下に敷き込むタイプの遮音材、わんぱく応援マットは合板フローリングとの組み合わせでLL40、無垢フローリングと組み合わせてLL45の遮音が取れています。
マンション床の防音対策に効果がある「わんぱく応援マット」ってフカフカしないの?
わんぱく応援マットはフェルトを圧縮したものと、ゴムの二層構造です。フローリングのように硬いと遮音が取れないので、多少の弾力性はありますが、フワフワするという感覚はなく、沈み込みもありません。そのため、しっかりとした踏み心地と高い防音効果両方欲しい!という方におすすめのマットです。
防音力の高いマンションの特徴は?
防音には床・壁・窓の設えが大きくかかわってきます。木造よりも鉄筋コンクリートのマンションのほうが音が伝わりにくいですが、鉄筋コンクリートのマンションでも床や壁の厚み、窓ガラスの仕様や窓のサッシのグレードにもよりますのでそのあたりもチェックしてみるといいですね。
防音性の高い部屋の見分け方は?
四方を囲まれているより、角部屋など隣接する部屋が少ない物件がおすすめです。また構造や間取りの確認も必要で、寝室がトイレや洗面所など排水管が近くに位置している場合、水音が聞こえる場合があるので注意が必要です。クローゼットや物置などクッションになる空間があると防音になります。また周辺に車通りが多い場合、窓に面した場所に道路がある物件は窓やサッシの防音がきちんとされているか確認しましょう。
無料で、資料・サンプル差し上げます
アトピッコハウスは、無垢・珪藻土・漆喰・クロス・畳など
オリジナルの自然素材内装材を、製造販売する会社です。